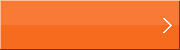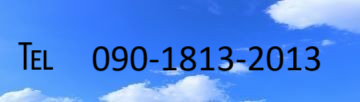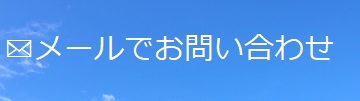- ホーム
- 未来社会保険労務士事務所ブログバックナンバー
未来社会保険労務士事務所ブログバックナンバー
1人だけワクチン打たない人
コロナウイルス関連のご相談、まだまだ多いという印象です。
ワクチン接種や、その後の副反応が出た際のお休み、また、濃厚接触者になってしまった際の対応、などなど。
「社員全員接種しているのに、一人だけ打ちたくないという人がいる。
そんな協調性がなくて、これから皆とやっていけるのだろうか?」
というご相談もありました。
言うまでもないですが、ワクチン接種と協調性は関係ありません。
ワクチン接種した方でも、協調性のない方はいくらでもいると思います。
逆に、協調性だけでワクチン接種するというのも怖い気がします。
ただ、重圧や責任感の中で摸索する経営者さんの心情を考えながら、いろいろな角度からお話を伺いご回答させていただいております(*'▽')
健康保険証の直接交付について
すでにご存じかもしれませんが、健康保険証の直接交付が始まります。
これまで、健康保険証の送付は、保険者(協会けんぽや健康保険組合など)が事業主に送付し、事業主から被保険者に送付することが義務付けられていました。
しかしテレワークなどの普及により、10月1日からは、事業主を経由せずに、保険者から被保険者に直接交付されることが可能となります。
実際には各健保組合で、送付費用はどうなる?などの調整が入るため、一斉に直接交付に切り替わるわけではありません。会社の定期健康診断
健康経営でご支援している会社の方から、こんなお悩みをお聞きすることがあります。
「健康診断を受けたがらない社員がいるのですがどうしたら良いでしょう?」
私も会社の人事部で勤務していた頃、受けたがらない方はいらっしゃいました。
自分の勝手だと言い切る方から、面倒だからという方まで、理由は様々です。
会社の定期健康診断の実施が、安全衛生法で定められていることは、ご存知の方も多いと思います。
じつは従業員の方にも、これを受診する義務があります。(労働安全衛生法第66条第5項)
労働時間が短いなどの理由で会社で受診しなくて良い人にも、自己保健義務というものがあります。
労働者である以上は、自分の健康に注意を払う必要があるってことなんです。
健康は自身のためだけではなく、周りで働く人たちのためでもあります。令和3年のご挨拶
新年のご挨拶が遅くなりましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします!
さて、皆様は今年の抱負を立てましたか?
目標を決めると、そこに向かうか、または近くまで行けるようになるので、立てる方が断然、お得ですよ!
政府も計画を立てた通り、今年の4月からは中小企業の同一労働同一賃金が施工されます。
元々政府は同一労働同一賃金の次に、完全デジタル化を軌道に乗せると決めていました。
その計画も着々と進んでおり、労基署に届け出る36協定届は、今年の4月から様式が変わり、押印、署名が不要となります。
同一労働同一賃金なんて無理!
と思ったあなたは甘いです。
遡れば、昭和61年に施工された男女雇用機会均等法も、当時は、
「男女の役割が違うのだから実際には無理!」
思った人も多かったのではないでしょうか。
なぜここまで実現したのかといえば、やると決めたからです。
何もしなくても同じように時間は過ぎますから、素敵な計画を立てましょう(^-^)/
社会保険労務士の活用
「社内に活気がない」
「慢性的な長時間労働がある」
などの問題がある会社さんで、今回、健康経営の一環として、全従業員の面談をさせていただきました。
社内の人間には話しにくいこともあるだろうから、ということで、一人ずつ対私でしたが、社長の判断は大正解。
お話を聞いていると、いろいろなことが見えてきました。
・経営者側と従業員側の考えていることに大きな食い違いが見られた。
・経営者がさんざん伝えてきたことが、従業員にほとんど響いてなかった。
などなど。
長期戦にはなりそうですが、長時間労働の解決の糸口も見えてきています。年次有給休暇の時季変更について
今回のテーマは年次有給休暇(有休)の時季変更権についてです。
これ、けっこう勘違いが多いところなんですが、
業務が忙しい時は、会社は有休の日程変更をさせることができる、と思っている会社さんが時折見受けられます。
就業規則にも、「業務の正常な運営を妨げる場合は時季を変更させることがある」などと記載されていたり。
あなたは、この記載のどこが違っているかわかりますか?
正しくは、「業務」ではなく、「事業」です。
事業の正常な運営を妨げる場合においては、時季を変更させることが認められています。10月の給与は要注意
毎年行われる社会保険料の改定。
改定された保険料が反映されるのは、その年の9月分の社会保険料からです。
では9月分の社会保険料は、給与計算のタイミングはどこで控除するのでしょう?
社会保険料を当月徴収している会社であれば9月、
翌月徴収の会社であれば、10月の給与計算で控除すれば良いことになります。
今年は算定の反映に加えて、厚生年金保険料の上限額の改定もあります。
厚生年金の標準報酬月額、これまで62万円だった上限が、65万円に引き上げられています。
引き上げられる該当者がいれば、その該当者と会社の保険料負担額が増えるということ。
そして該当者の、将来受けとれる年金額が増えるということです。
失業手当の給付制限期間が変更になります
雇用保険の失業手当は、自己都合で退職した場合、3カ月間の給付制限がかかります。
この3カ月が、10月1日より2カ月に短縮されます。
自己都合退職の場合、給付制限は9月30日で退職すると3カ月、10月1日以降だと2か月、ということになります。
企業においては実務上の影響はありませんが、退職予定者にはアナウンスした方が良いでしょう。
なお、5年間のうち2回の離職までという制限つき、さらに、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職の場合は、これまでどおり3カ月です。
労災に馴染みがない理由
国でやっている保険は、大きく分けて4つあります。
雇用保険
労災保険
年金
健康保険
このうちなぜか、労災保険(業務でケガをした時などのための保険)に関して、時折、従業員の方だけでなく、経営者の方からも、
私が思う正解はこちら。
労災保険だけは、給与からの控除がないから。
雇用保険、厚生年金、健康保険などは、控除欄に記載があり、いくらか控除がされていると思います。
もちろん、勤務形態、時間などによっては要件にあてはまらず、加入することができないため、お給料から引かれることもありません。
しかし!!!
労災は、雇用されていれば必ず、適用になるんです。
それなのに、お給料から労災保険料料が引かれることはありません。
なぜなら、労災保険料は、全額事業主の負担だからです。
同一労働同一賃金
今回のテーマは同一労働同一賃金です。
時折、社労士の電話相談室の相談員をさせていただくことがあります。
先日の担当時、コロナ関連のご相談もある中で珍しく、同一労働同一賃金(以下、同一労賃)についてのお問い合わせがありました。しかも、労働者側から!
察するところ、ご自身の待遇に不満があり、同一労賃を皮切りになんとか会社をギャフンと言わせたいようで(表現が昭和(^-^;)、
こちらの発言に
「では会社は違法ってことですよね?」
と敏感に戦闘態勢に。
同一労賃といっても正規社員と非正規社員の給与がまったく同じになるわけではなく、
その手当(職務手当、通勤手当、皆勤手当など)の内容により個別に判断されます。
たとえば通勤手当は、通勤の費用を補助するための手当であり、正規、非正規で差をつけることは違法です。
でもたとえば、会社の事情でパートだけは近隣区域からしか募集していない場合などは、この限りではありません。
「何に対する賃金か」で判断し、同じか又は責任の度合いなどに応じてバランスのとれた手当が求められます。
今回の同一労賃で大きく変わった点として、会社には待遇差の内容の説明義務が求められますので、
何か疑問があれば、会社に聞いてみましょう。
会社も気づかない点があるかもしれないので、攻め立てるのではなく、温和に質問すると良いでしょう。
そもそも厚生労働省のガイドライン通りに設定している会社の方が少ないと思います。
同一労賃、中小企業は2021年4月から適用されます。
準備ができていない会社は給与規程の見直しをしておきましょう。
- 給与計算だけをアウトソーシングしたい
- 健康経営に興味がある
- 自分の会社にあったサポートをしてもらいたい
こんなときはご連絡ください。
未来社会保険労務士事務所
まずはお気軽にお問合せください。
電話番号:090-1813-2013
所在地 :東京都北区王子6-2-6-201
定休日 :土日祝